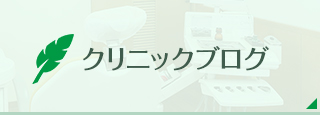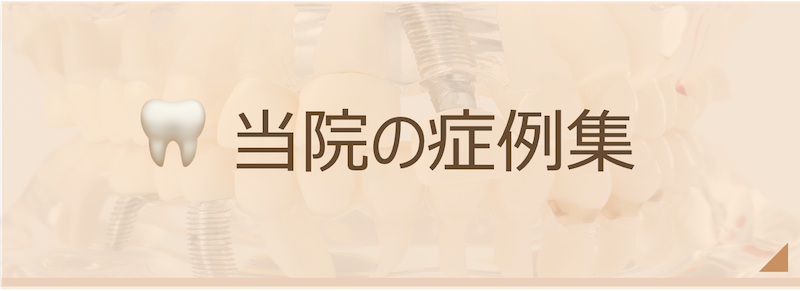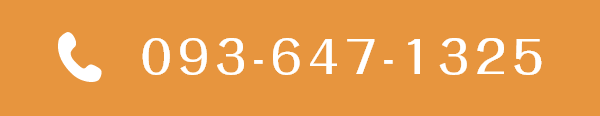誰もが一生健康で楽しく過ごしたいと願っています。お口の中の歯が残っている本数が多い人ほど元気で自立しているといわれています。自分の歯でしっかりかんで食べることが元気な体をつくります。また自分の歯が残っている方の方が認知症にもなりにくいといわれています。
誰もが一生健康で楽しく過ごしたいと願っています。お口の中の歯が残っている本数が多い人ほど元気で自立しているといわれています。自分の歯でしっかりかんで食べることが元気な体をつくります。また自分の歯が残っている方の方が認知症にもなりにくいといわれています。
ところでお口の健康を考えたとき、むし歯や歯周病の症状(痛い、しみる、膿がでる)を気にします。
しかし、原因であるプラークの中に含まれている細菌を毎日飲み込んでいることには無関心です。
近年の研究ではお口の中の細菌が血液や歯周組織から体内に入り、全身疾患の発症に関与しているといわれています。つまり全身の健康維持のためにはプラークの除去は必要なことが分かってきています。プロによるお口のチェックを受けて、定期的にクリーニングしてもらいお口の中が清潔になるようにしましょう。お口のケアはアンチエイジングの基本です。
8020運動について
「80歳まで自分の歯を20本残しましょう」という8020運動の達成率は実際は約30%でした(平成17年)。過去のデータと比較すると平成5年度の約2倍、平成11年度の約1.7倍です。
だんだん良くはなってきてはいますが、予防先進国の欧米に比べると日本はまだまだです。
歯周病は増えている?
55歳以上では歯肉に炎症がある人の割合が増加しています。診査が厳格化してきたことと、残っている歯の本数が多くなったことで数値が増えたようです。若い人ではお口の健康への関心の高まりを反映して歯周疾患が減っています。

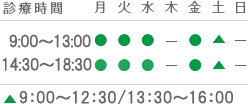

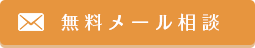
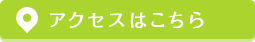




 どの症状には注意が必要です。お食事が満足にとれないようになると全身の健康に影響します。
どの症状には注意が必要です。お食事が満足にとれないようになると全身の健康に影響します。