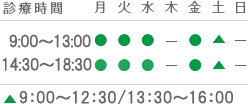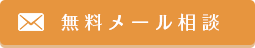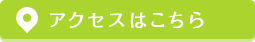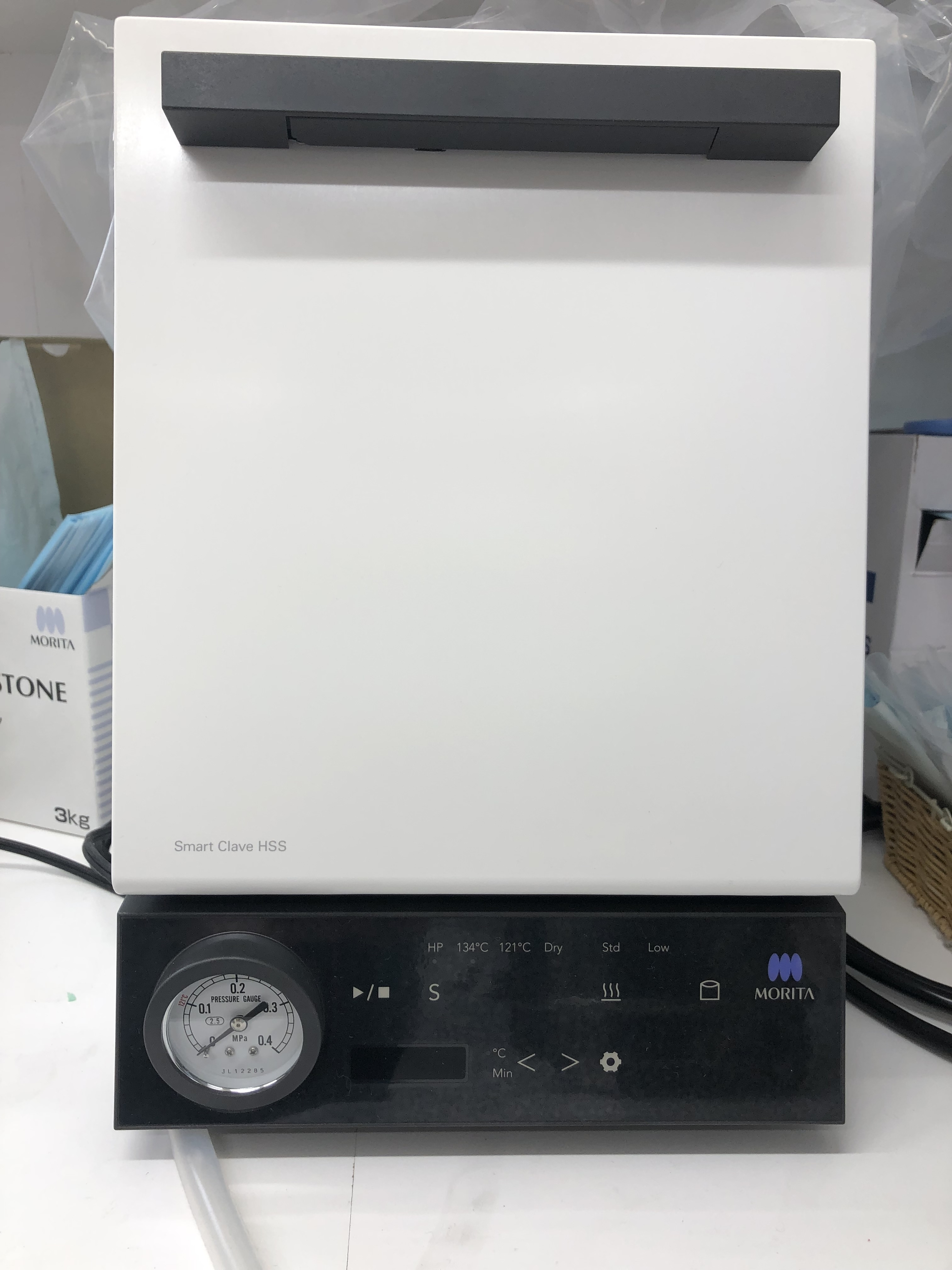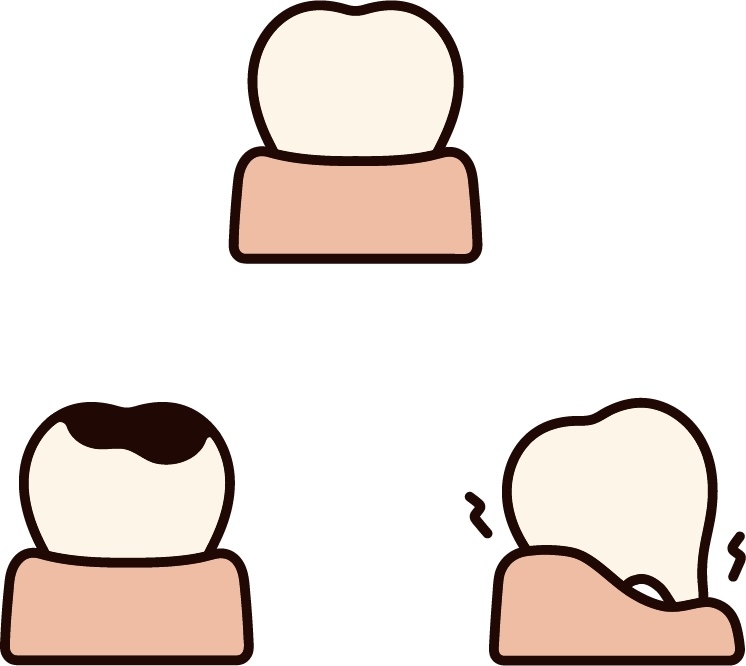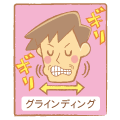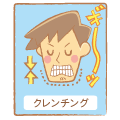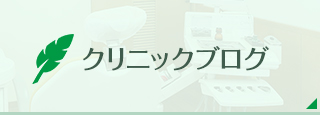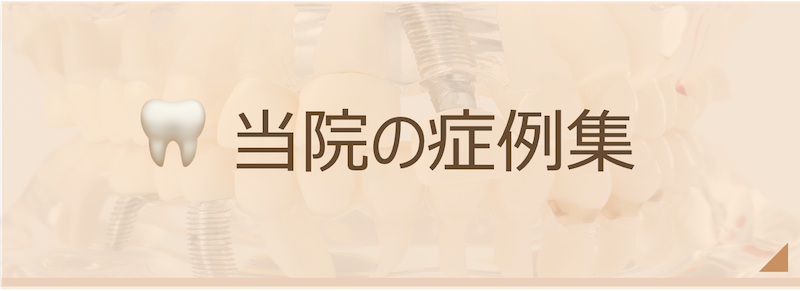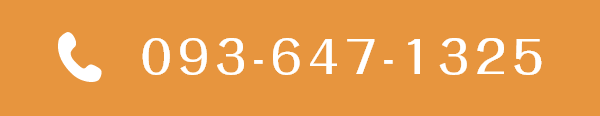こんにちは。八幡西区の歯医者いまむら歯科クリニックです。
今回は口腔機能低下症についてお話をしたいと思います。
元気で長生きのためにはお口の機能の維持、向上が大切です。高齢者の多くの方は口腔機能の低下を実感しているが具体的な意識を持っていることは少ないようです。
口腔機能低下症とは2016年に日本老年歯科学会が「高齢期における口腔機能低下症の定義と診断基準」として公表し、2018年に保険収載された歯科で最も新しい病名のひとつです。
口腔機能低下症を見過ごしてしまうと咀嚼障害、摂食嚥下障害となって全身的の健康に影響を及ぼします。①口腔衛生状態不良、⓶口腔乾燥、③咬合力低下、④舌口唇運動機能低下、⑤低舌圧、⑥咀嚼機能低下、⑦嚥下機能低下などの検査をおこない3項目が該当する場合口腔機能低下症と診断します。口腔機能低下症は咀嚼障害、嚥下障害などの障害レベルより前の段階とされており、口腔機能の低下に対する自覚症状が少なく見逃してしまいがちです。

口腔機能の大切さ
口腔機能が健全でないと様々な影響を全身へ及ぼします。オーラルフレイルが全身のフレイルに影響を与えます。ある調査では口腔機能が健全な方に比べて、オーラルフレイルは身体的フレイルを2.4倍に上昇させます。口腔機能低下症の検査のひとつである口腔衛生状態不良、口腔乾燥、残存歯数、舌圧、舌口唇運動機能低下の5項目の該当数と栄養状態との関係を調査した研究では、低栄養状態と関係性があることがわかってきました。
以下のような症状がある場合口腔機能低下症の可能性があります。
① 硬いものが食べにくくなった
② 汁物を飲むときに時々むせるようになった
③ 口の中が乾くようになった
④ 薬を飲みにくくなった
⑤ 滑舌が悪くなった
⑥ 食事をするのに時間がかかるようになった
⑦ 食べこぼしをするようになった
⑧ 食後に口の中に食べ物が残るようになった
日常生活におけるささいなお口の機能の衰えなどを放置しておくと、楽しく会話をしたり、十分な食事をとることが出来なくなり、心身の活力の低下を引き起こしてしまいます。
口腔機能を検査して機能の維持、改善をしていくようにしましょう。
口腔機能低下症の管理
口腔機能低下症の管理は患者さんに自身の口腔機能の状態を知っていただき、その機能の維持、向上に対する動機づけから行っていきます。それによって患者さんの日常生活における意識の変化が見直しへと繋がっていきます。
「少しでも歯ごたえのあるものを食べる」「毎日ぶくぶくうがいをする」など日々のちょっとした行動が大切です。
口腔機能低下症によって引き起こされる重篤な症状に代表的なものとして誤嚥性肺炎があります。ここからは「肺炎」と「誤嚥性肺炎」についてお話させて頂きます。
肺炎は死因別死亡率の第4位を占めるほど重篤な疾患と言われています。その9割以上が65歳以上のご高齢者が占めています。さらに肺炎の年齢階級別死亡率は70歳以上で急激な増加傾向を示し、ご高齢者にとっては大きな転帰を引き起こしてしまいます。
肺炎は長期入院患者の感染症としては尿路感染についで多くその感染経路は口腔内細菌の誤嚥、「誤嚥性肺炎」の存在が考えられます。また口腔内環境が悪いと肺炎の発症を助長することも研究の結果から分かってきました。高齢者における比較対照の研究では、口腔ケアをしっかりと行なわなければ肺炎の発症率が高くなることが報告されています。そのため感染源を減少させ、肺炎の発症を予防するためにも口腔ケアを行い口腔の細菌を減らすことが大切です。
「誤嚥」とは?
「誤嚥」とは食べ物や唾液、胃からの逆流物や異物などが気管に入った状態をいいます。なお正確には声門より下に入った場合を誤嚥、声門より上の気道までの侵入は咽頭内侵入とよんでいます。似たような言葉で「誤飲」とありますがこれは子供などが誤って異物(小さなおもちゃなど)を飲み込んでしまって食道に入ることをいいます。
「確実に誤嚥性肺炎」であるという場合は明らかな誤嚥が直接確認された後に肺炎になった場合、もしくは肺炎を起こしていて誤嚥物が吸引などにより確認された場合にあてはまります。
「ほぼ確実に誤嚥性肺炎であろう」という場合は飲食の際、摂食・嚥下障害を起こす可能性の高い基礎疾患を持っていてそのうえで肺炎を起こしたような場合です。
私たち歯科医院でできること…
「誤嚥」は大きく3つに分けられます。「唾液の誤嚥」「食物の誤嚥」「胃などからの逆流物の誤嚥」。
「唾液の誤嚥」に関しては口腔ケアを行うことによって、唾液中の細菌を減らすことが重要になります。「食物によって誤嚥を起こしている場合」には、誤嚥しにくい形態へ食物を変更する、誤嚥したものが自然と吐き出せない場合、食事中にときどき咳をしてもらう、誤飲防止のために舌などを鍛える。などの対応が必要になります。
「胃などからの逆流物の誤嚥」については、食後すぐに横にならないようにする、胃瘻などから栄養をとっている患者さんは注入する栄養剤を硬さを変えて逆流しにくくするなどの対応が必要です。
誤嚥性肺炎の発症を予防するには口腔ケアによってお口の中の細菌を減らすことが大切です。