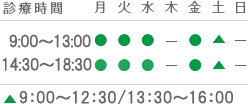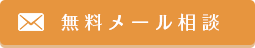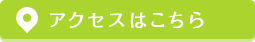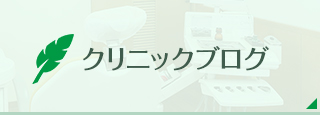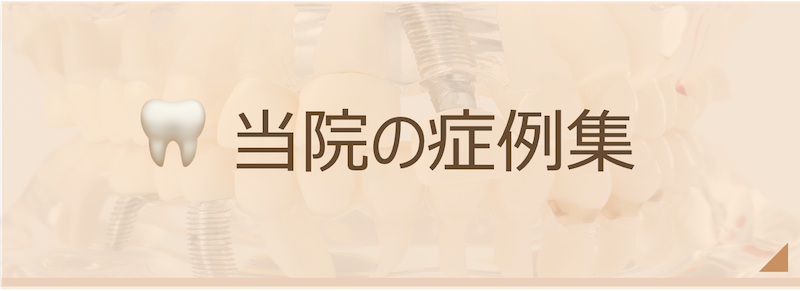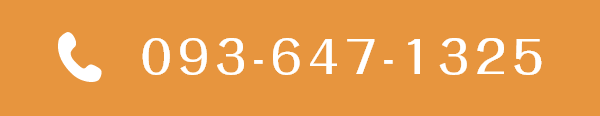八幡西区の歯医者いまむら歯科クリニックです。
さて今回は親知らずについてお話しをしましょう。
みなさん親知らずってご存知でしょうか?奥歯の一番後ろに生えてくる歯のことです。親知らずの名前の由来は親知らずは20歳くらいで生えてきます。親の手のかからなくなったころに生えてくるので「親知らず」また知恵がついたころに生えてくるので「智歯」といわれています。また昔は今ほど寿命が長くはなく20歳くらいになると親がすでに亡くなっていたりするのでこのように言われるようになったという説もあります。
「私は親知らずがない」というかたもいらっしゃるかと思いますが、もしかしたら歯ぐきの中に埋まったままなのかもしれません。また親知らずが最初から無いかたもたまにいらっしゃいます。
歯科医院で一度親知らずは抜いたほうがいいですよといわれ、別に痛みもないし、抜くのは痛そうだしとそのまま放置していませんか?横に生えていたりして問題のある親知らずはただ歯ぐきに炎症を起こすだけではなく、手前の第二大臼歯を失う原因にもなります。
むし歯ができて放置したままだと抜歯をする際、掴むところがなく抜歯を困難にしたり、年齢を重ねると歯と顎の骨の癒着がおきてなかなか抜けなかったりします。
抜歯をするなら若くて体力があるときにした方が良いでしょう。
永久歯は12歳ごろに上下28本が生えそろいます。そのあと16~18歳ごろに「親知らず」が生えてきます。親知らずの生え方には個人差があり、上下4本全部生える方から全く生えてこない方まで様々です。中には先天的に生えてこない方もいます。この原因は現代の柔らかい食生活によってあごの骨が十分に発達しないため、歯がきれいに並ぶスペースができないからだといわれています。
親知らずは生え方によって周囲の歯や歯肉に炎症を起こしたりすることがあります。

前の歯を圧迫すると…
親知らずは手前の第二大臼歯を圧迫することがあります。その影響で全体の歯並びが悪くなることがあります。
親知らずは現代人では萌出するスペースがなく、顎の中に埋まったままで出てこなかったり、出てきても少しだけで完全に出てこなかったりします。そのため、親知らずの周りの歯ぐきに炎症が起こりやすくなります。また、物が詰まったりして親知らずのひとつ前の歯がむし歯になったりします。このように下顎埋伏智歯(下顎に埋まったままの親知らず)は感染症を誘発するほか、顎の骨の骨折を誘因したり嚢胞の原因となったりします。
よく親知らずが原因で歯科医院に来られる方は親知らず周囲の歯肉が痛い、腫れたという『智歯周囲炎』の方がほとんどです。この様な症状の場合、患部を消毒して抗生物質を数日服用して頂くと痛みや腫れは治まってきます。しかし痛みや腫れを繰り返すなら抜歯した方がよいでしょう。
抜歯することにより親知らず周囲の歯肉の痛みや腫れはなくなり、親知らずの隣の歯がむし歯になるリスクも下がります。
抜歯した際には痛みや腫れをともなうことがあります。また、親知らずが深い位置に埋まっているときなどは個人医院での抜歯が困難なこともありますので、大学病院などへ紹介させていただくこともあります。
【親知らずの抜歯の流れ】
①レントゲン検査を行います。深い部位に埋まっている場合や歯の根っこが曲がっていたり複雑な形態をしている場合はCT撮影を行います
②来院時に歯ぐきが腫れている、痛みがあるときは抗生物質を服用し、炎症をおさえてから抜歯をします。炎症がある状態だと麻酔が効きにくい、抜歯後感染を起こすことがあるためです
③抜歯は局部麻酔を使用して行います。抜歯時間は程度によりますが20~40分くらいです。歯ぐきに埋まっているときは歯ぐきの切開や骨削合が必要になります
④抜歯後に数回患部の消毒に来ていただきます
⑤通常抜歯後1週間程度で糸取りを行います