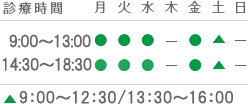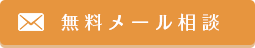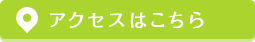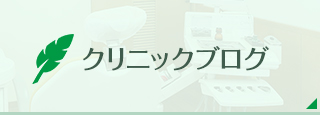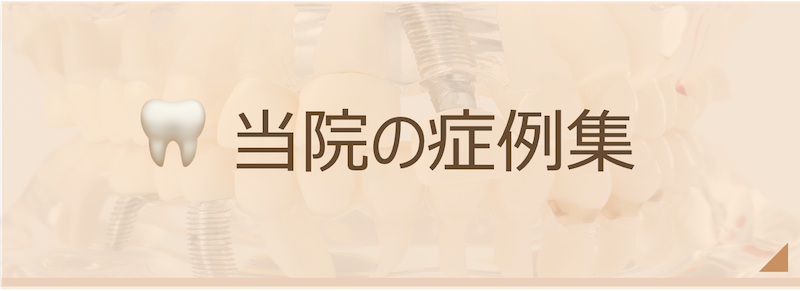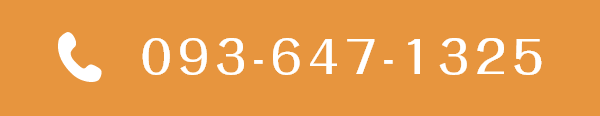八幡西区の歯医者いまむら歯科クリニックです。
唾液には再石灰化作用(溶けた歯の表面を元に戻す)や潤滑作用(咀嚼・嚥下を容易にする)がありますが、唾液が減ってしまうとその恩恵が受けられません。虫歯や誤嚥のリスクが高くなるので、注意が必要です!お口の乾燥が気になる方も是非、1度試してみて下さい。
今回は「噛む」という行為についてお話ししたいと思います。

1回の食事で何回噛んでいるか、みなさんご存じですか?
現代の食事は600回です!
・・・と言われても、多いのか少ないのか分からないですよね。時代を遡ると、江戸時代は1000回、鎌倉時代は3000回、縄文時代はなんと4000回も噛んでいたそうです。
1回の食事で4000回噛んでいる縄文時代の人でも、見つかった歯のうち虫歯の確率は9%以上。そんな時代から虫歯はあったんですね。植物を主食とする食料採集民に多いそうですが、世界的にも高い虫歯率みたいです。
もっと遡って原始時代には虫歯が存在しなかったそうです。なぜなら原始時代の調理方法といえば「焼く」くらいで、ほとんど硬い物しか口にしなかったからです。
硬い食べ物は必然的に噛む回数が増え、その分唾液が分泌されます。唾液の水分によって虫歯菌が好きな糖質を洗い流し、食べることで酸性になる口の中を中性に戻す作用が働き、虫歯や歯周病を防いでいるのです。
それから「煮る」「炊く」などの調理法を人類が覚えて食べ物が柔らかくなると、噛む回数も減りはじめました。同時に柔らかい食べ物は歯にこびりつきやすく、虫歯や歯周病の原因となる歯垢(細菌の塊)が生じやすくなります。
そして、虫歯・歯周病にかかりやすいお口の状態になってしまうのです・・・
付いた歯垢は歯ブラシ、歯間ブラシ、糸ようじなどで磨いて落とせますが、完全に落とすことは出来ません。もちろん歯磨きも大切なのですが、よく噛むことでお口の中に歯垢が付きにくい環境を作ってみませんか?歯磨きも楽になると思いますよ。
・食事の噛む回数を増やすために…
ひと口の量を減らす
食事の時間に余裕を持つ
まずは噛む回数を5回増やす
食材は大きく、厚めに切る
歯ごたえのある食材を選ぶ
薄味にする
・咀嚼回数を補うために、ガムを噛む
お口以外にも、よく噛んで唾液が分泌されることで、肥満を防ぐ、認知症の予防、がんを防ぐなどの全身を活性化するのに重要な働きをしています。
今年はよく噛んで、虫歯・歯周病を防いでみませんか?
それでは虫歯予防、歯周病予防のため、成人期のお口についてお話したいと思います。
成人期は20代~60代と幅広い層になるので、分かりやすく20代と50代でお話をします。▫20代のお口▫
全ての歯は28本で、親知らずを含むと32本。20代の平均は29本で人生で1番歯が多い年代です。ですが、歯には虫歯で治療している多数あるのが特徴です。歯の溝が深くなったり、歯の色の黒ずみや水がしみる事か気になった場合は要注意です。歯科医院でみてもらいましょう。歯ぐきには、歯ぐきのみの軽度の炎症=歯肉炎(軽度歯周病)か58%の人に。歯の周りの組織への影響がある歯周炎(中度~重度の歯周病)が約8%います。お口がネバネバしたりハミガキで出血することや、口臭がするようになった方は歯周病の可能性があります。歯石取りやメンテナンスをしましょう。20代に多い初期の歯周病=歯肉炎は適切な治療でもとのように治ります。
▫50代のお口▫
50代後半になると急激に歯の減少が目立ってきます。
ただこの年代に急にお口の状態が悪くなるのではなく、これまでに徐々に歯周病が進行した結果と適切な治療を受けなかったことが原因で歯がなくなります。25歳以降から歯周炎(中度~重度の歯周病)の割合が増えて、45~54歳あたりでピークになります。(ピークと言うのはその後は歯の本数が減ってくるので割合は減りますが、歯周病が治るわけではありません。)症状としては出にくいのですが、
・「歯が動くようになった」
・「歯の間の隙間が増えた」
・「硬いものが噛めなくなった」
・「歯ぐきが腫れる」
・「口臭が強くなった」
・「膿が出る」
などがあります。
症状で気になることがある方は早めに歯科医院で精密検査を受けましょう。
成人期・大人のお口では虫歯ももちろんですが、歯周病との関係が深い事が分かりますね。いまむら歯科クリニックでは、歯が抜けてなくなる可能性を下げる為に予防歯科に力をいれています。20代から始まる歯周病で歯が抜けることがないように、定期検診やメンテナンスを是非ご相談ください。 歯学博士 今村英之