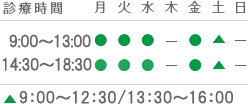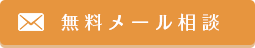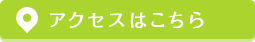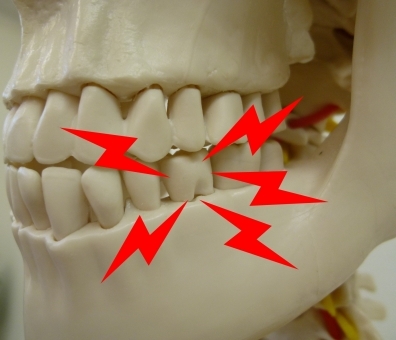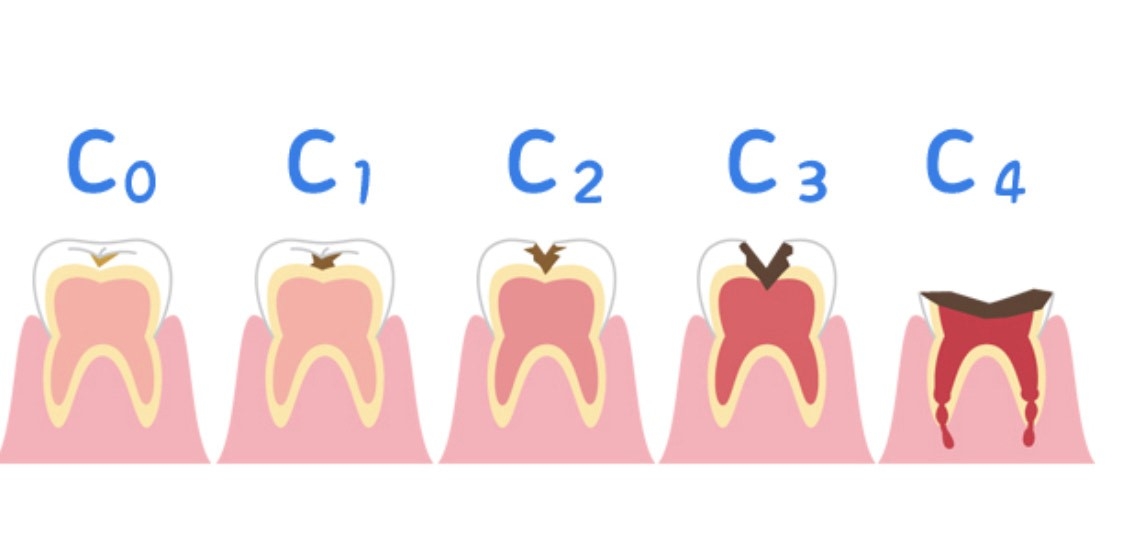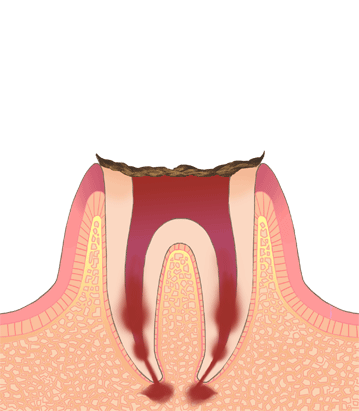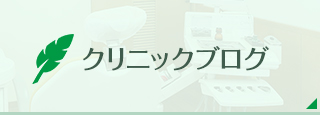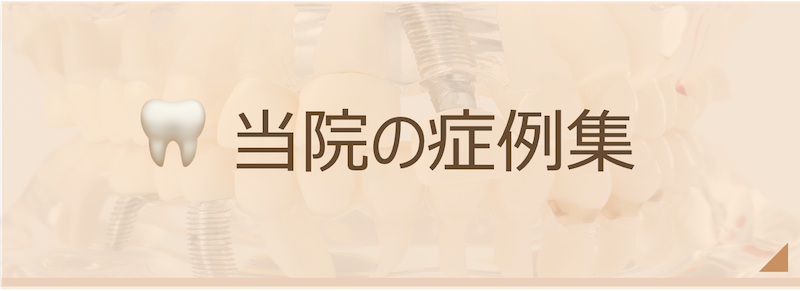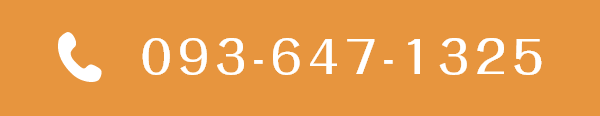こんにちは。八幡西区の歯医者、いまむら歯科クリニックのスタッフの和田です。
急にすみません。我が家の出来事なのですが、私の子供君が学校で今、きゅうりを育てているらしく、毎日学校から帰ってくるたびに育てているきゅうりの成長について話をしてくれます。
今日花が咲いたよ。今日は小さい赤ちゃんきゅうりが2つも出来たよ。こーんなに大きくなったよ。収穫して持って帰ってきたらカッパ巻きを作ってね。と笑顔で話をしてくれているので、お家でも何か野菜育てるか聞くと…無の顔になって別にと返されました。あんなに楽しそうに話してくれていたのにまさかの答えで、子供の考えている事思っている事は未だに分からないものです。
さて、みなさん。分からない事といえば、歯ブラシの交換は、どの位の頻度で交換していますか?歯ブラシの交換するタイミングが良く分からない方がほとんどだと思います。患者さんからも良く質問されます。
今回は、歯ブラシの交換のタイミングについてご説明させていただきますね。

歯ブラシは、毎日毎食後に使用する消耗品です。
そのため、だいたい歯ブラシの寿命交換目安は、約一ヶ月とされています。新品の歯ブラシで磨いて落ちる歯垢(プラーク)を、100%とすると、毛先が少し開いた歯ブラシで磨くと80%ほど、毛先が外側にペラっとパックリ開いた歯ブラシになると60%程度しか汚れ歯垢(プラーク)が落ちないと言われているそうです。
なので清掃効果を高めるためにも歯ブラシの交換が必要なのです。
交換せずずっと同じ歯ブラシを使用し続けるとデメリットがあります。
①歯ブラシの性能が下がる
・新しい歯ブラシは、毛先が真っ直ぐ立っているので、毛先が歯と歯の間、歯と歯茎の境目にしっかり入り込み食べカスや歯垢(プラーク)をかきだしてくれます。
しかし一方で、同じ歯ブラシを使い続けていると徐々に歯ブラシの弾力が失わられボサボサに広がり、いつもと同じ様に当てていても十分に汚れを落とす事が出来ず、虫歯や歯周病になりやすくなります。
②歯にダメージを与えてしまう
・歯の表面は、エナメル質という硬い組織に覆われています。歯の表面は、過度な歯ブラシの圧がかかるとダメージを受けます。
歯ブラシを持つ力は、歯ブラシのグリップを鉛筆の握り方で軽く握ります。歯ブラシを歯面に押し当てる圧も小さくて済みます。
が、同じ歯ブラシを使い続けると清掃効果が低下してしまい、無意識に圧を強く磨いてしまい歯にダメージを与えてしまうリスクが上がります。
歯ブラシは、毎日毎食後使用する物です。
出来るだけ清潔に保つ事が大事です。
歯磨きをした後は、しっかり流水で歯ブラシの汚れを落として下さい。そして、歯ブラシの頭を上にしてしっかり乾燥の出来る所で保管をして下さい。ただ、歯ブラシのケアをしっかりしていても、同じ歯ブラシを長い間使い続けているのは、不衛生ですのでだいたいの歯ブラシの交換目安を1ヶ月ほどをおすすめします。
定期的な検診の時に、歯ブラシを購入し交換する目安としても良いかもしれませんね。
ご自宅でのケアの為にも来院お待ちしていますね♪