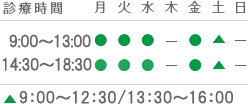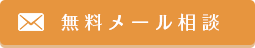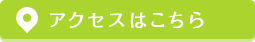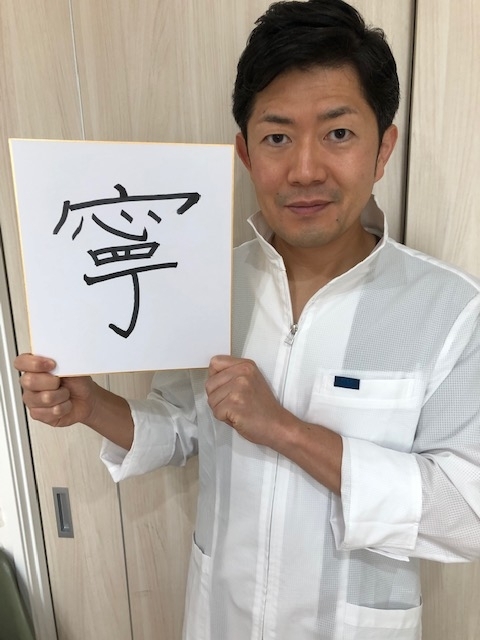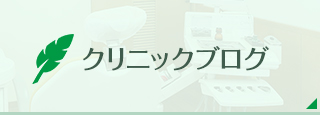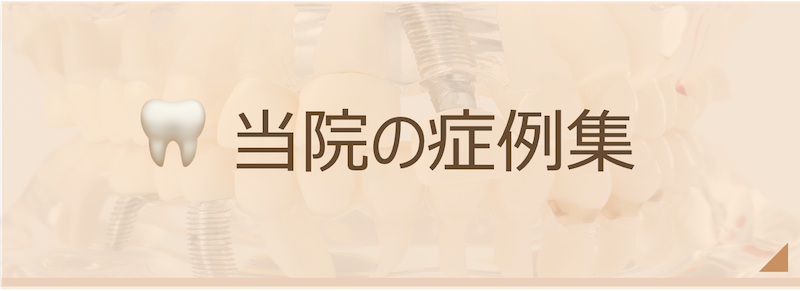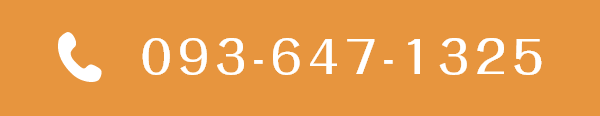こんにちは、八幡西区の歯医者いまむら歯科クリニックスの平田です。
4月18日は「良い歯の日」でした。
良い歯とはどんな歯のことしょうか。
例えばむし歯がない、歯周病になっていない、噛み合わせに問題がない、歯並びが揃っている、歯の色が白くてきれい、などが考えられると思います。
その中でもむし歯は、子供から大人まで誰でもかかりやすいお口の中の病気だと言えます。

今回のブログは、むし歯の予防策として代表的なフッ素塗布についてお話しさせていただきます。
フッ素塗布と聞くと、歯医者で定期検診を受けた際や小学校で塗布した思い出があるかと思いますが、もっと簡単にご自宅で塗布できる「チェックアップジェル」をご紹介したいと思います。
まず、私たちが食事をするたびに、歯のカルシウムやリンが溶け出す「脱灰」と、唾液が溶けた成分を元に戻す「再石灰化」を繰り返しています。
この「脱灰」がむし歯になるきっかけを生むのですが、フッ素を塗ると「再石灰化」を促進させることができます。
【フッ素の効果】
1 歯を強くします
フッ素が歯に取り込まれて、むし歯になりにくい強い歯を作ります。
2 歯の再石灰化を促進します
歯に穴があいたり、黒くなってしまったむし歯は治療しないと治せませんが、歯の表面が白濁した程度の初期むし歯なら、自然治癒を助けてくれます。
3 むし歯菌を抑制します
フッ素がプラークの中に入って、歯を溶かす原因である酸が作られるのを抑えてくれます。
【チェックアップジェルの使用方法】
まず、食事のあと歯を磨きます。
うがいができるお子さんは、フッ素が入った歯磨き剤を歯ブラシに取ってよく磨きうがいをします。
まだうがいが上手くできない小さなお子さんには歯磨き剤は使用せずに歯ブラシだけで磨きます。
歯磨きが終わったらフッ素ジェルを歯ブラシに取って、全ての歯に行き渡るように軽く磨きます。
塗布後は口をゆすがず、そのままか軽く唾を吐き出す程度にします。
そのあと最低30分間は飲食されないで下さい。
夜はフッ素ジェルを塗布したら、そのまま就寝するのがベストです。
因みに乳歯が生えたらすぐのタイミングでフッ素を塗るのが最も効果的だとされています。
生えたての歯は柔らかく、簡単にむし歯になってしまいますので、歯が生えたら出来るだけ早くフッ素ジェルを塗りましょう。
【使用量】
年齢に応じて適切な量を使用します。
2歳までは歯ブラシの毛先に2mm程度だけ出して歯に塗布します。
3〜5歳で5mm程度、6〜14歳で1cm程度、15歳以上で2cm程度を使用します。
【フッ素濃度の違い】
チェックアップジェルには5種類の味があります。
それぞれフッ素濃度が違いますので、年齢によって選ぶようにして下さい。
・バナナ(500ppm)5歳まで
・グレープ(950ppm)6〜14歳まで
・ピーチ(950ppm) 〃
・レモンティー(950ppm) 〃
・ミント(1450ppm)15歳以上
どれも、ほのかな味と香りで後味がスッキリしています。
歯磨きができたご褒美に塗ってあげると、歯磨き嫌いが治るかもしれませんよ?
そんな期待も込めつつ、子供から大人まで塗るだけでむし歯予防ができるチェックアップジェル、すごくおすすめです。
いまむら歯科クリニックで販売していますので気になる方はぜひ一度お試し下さい。