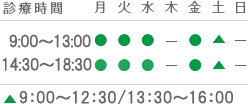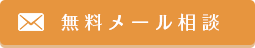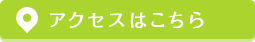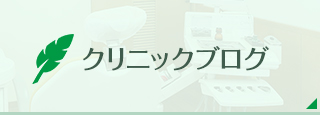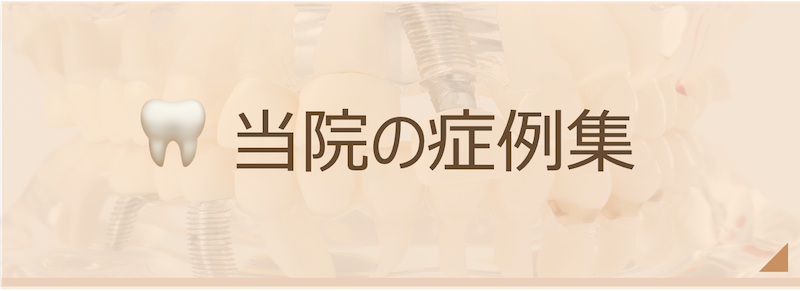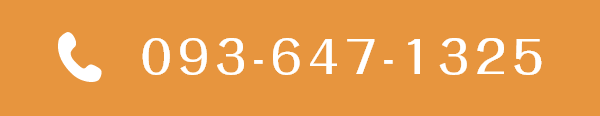こんにちは!八幡西区にある歯医者「いまむら歯科クリニック」スタッフの田中です。
日に日に秋が深まる季節となりましたが、みなさまいかがお過ごしですか。
先日、八幡歯科医師会主催のレクレーションに行ってきました♪
これは毎年行われているのですが、今年はうきは市の春光園さんでフルーツ狩り、朝倉市の原鶴温泉、泰泉閣さんでお昼ごはん(お風呂付き)という内容のバスハイクでした。
60名ほどの参加でしたので、バス2台で行きました。
いまむら歯科クリニックからは、院長先生、先生のお子さん2人、スタッフ4人が参加しました。
春光園さんは一年中フルーツ狩りが楽しめる農園だそうで、この時期は柿でした。
梨もできるかなと期待していたのですが、残念ながらすでに終わった後で(-_-;)
少しだけ販売していたので、早めに並んで梨もゲット!
スタッフはみんな梨を買えたのですが、院長先生は買えなかったらしいです(>_<)
柿狩りはみんな初めての経験でした。
日にたくさん当たっている高いところの柿の方が大きくて、きれいなオレンジ色をしているんです。それを採りたくて脚立やはしごを使い、さらには背伸びまでして・・(笑)
貴重な体験でした♪
泰泉閣さんの料理は、地元のものを使った懐石料理で、とても美味しかったです。
デザートの杏仁豆腐には梨で作ったソースがかかっていて、爽やかで斬新でした。
温泉は時間がなくてバタバタでしたが、露天風呂までちゃっかり入りました(笑)
さすがに帰りはみんなぐったり・・。
途中まで私も眠っていたのですが、トイレ休憩のパーキングでお土産買ったりと、最後まで充実していました。
バスハイクって楽でいいですよね~♪
運転もおまかせで、眠っていてもちゃんと目的地に着くし(笑)
ずっと笑いっぱなしで、とても楽しい一日でした♪
さて、今年も残り1ヶ月半。
お店ではすでにクリスマスグッズが並んでいて、そう考えると、年末、お正月と時の早さを実感します。
今年中にお口のクリーニングを終わらせて、スッキリした歯で新しい年を迎えたいものですね。

磨き残しがあると、個人差はありますが2日ほどで石灰化が始まり、そこから15日ほどで歯石になるとされています。
歯石は歯ブラシでは取れません。
また、虫歯がない、歯が丈夫だ、という方は歯医者さんには無縁で、検診などを受けなければ行く機会がありません。
そのせいか、虫歯が1本もないという方は歯周病が進行している場合が多いのです。
歯を失うリスクは、虫歯よりも圧倒的に歯周病の方が多いのです。
歯周病とは、歯を支えている骨(歯槽骨)が溶けてしまう病気で、一度溶けた骨はもう元には戻りません。
なので、いかに現状維持していくかが大切なのです。
歯石がついているとそこを住処とし細菌が繁殖します。
細菌を減らすには、毎日の歯磨きはもちろん、歯医者さんで歯石を取ることが重要です。
また、一度取っても3ヶ月くらいすると元の状態に戻るといわれていますので、その3ヶ月に合わせて汚れを落とすことで、よりお口の中を清潔に保てますし、もし虫歯になっても、早期発見早期治療で、早い段階での治療が可能となります。
いまむら歯科クリニックでは予防に力を入れています。
虫歯や歯周病を予防するためにも3ヶ月に1回はお口のクリーニングを受けましょう。